- Q今回の記事で学べる内容はなんですか?
- A
人と深い信頼関係を築くプロのスキルを学び使いこなせるようになる方法を学べます。しっかりと順序だてて学ぶことで驚くほど速くプロのスキルを習得できる内容となっております。
じっくりと想像してみて下さい。
もしも人と信頼関係を築く方法を身につけられたら、あなたの生活はどのように変化して行くでしょうか?
いかがでしょう?
きっと、今よりもはるかに素晴らしく輝いている未来の一片を感じられたのではないでしょうか?おそらく、地獄のような未来を創造された方はひとりもいないでしょう。
そうなんです。人と信頼関係を築くすべを身につければ、私たちの未来は限りなく拓けて来るのです。にもかかわらず、私たちが受けて来た教育の過程では「人との信頼関係の築き方」なんていう授業は記憶にありませんよね。
だから、信頼関係を築く技術を持っている人は、その人の持って生まれた性質によるところが大きかったりします。生まれつき社交的だったり、人の話を聞くのが好きだったり、要領がよかったりと・・・
ごく一部の【持っている人】だけが人と信頼関係を築くのがうまいというのがこれまでの常識ですよね。
でも、実は人と信頼関係を築く方法は後天的に磨き上げることが出来る技術なんです。しかも、何百時間と学ばなくてもコツさえ押さえておけばすぐに効果が実感できる優れた技術です。
ということで、今回の記事では人と信頼関係を築く方法についてお伝えして行きます。
Ⅰ.人と信頼関係を築くコミュニケーション術7選

人と信頼関係を築く上で外せないのがコミュニケーションです。当然ですよね。接点のない人とは信頼関係を築けるはずもないですものね。コミュニケーションを通して、相手を理解し、自分を理解してもらう事が信頼関係を築く上での第一歩です。
1.自己開示をする
スタンフォード大学スティーブンマーフィー重松教授が著書「スタンフォード大学マインドフルネス教室」において、ストーリーテリングの重要性を説かれています。この本に人との信頼関係を築く上でのヒントが記載されていたのでご紹介します。
授業でのストーリーテリングの活用は、脳への影響を立証した研究が裏付けを与えている。物語を聞いている時には、その物語を聞き手自身の考えや体験に変えてしまう脳の部位が活性化する。聞いている者同士の間で同じような脳内活動が行われるだけでなく、ミラーリングと呼ばれる作用によって、話し手とも同じような脳内活動が行われるのである。
ストーリーテリングをする事で、自らの体験を通して他者にも同様の感情が伝わります。ようは、自分と他者との間で共感が起こると言うことですね。
自らの衝動に触れた経験が大きいほど、相手との間に出来る絆の深まりは強くなるのです。自己開示をするという事は自分を相手に分かってもらえる事と、相手と自分に対して共感を通して絆が出来る事が大きな特徴です。
2.相手に好奇心を向ける
信頼関係を築く上で最も必要な要素のひとつに相手に対して好奇心を向けることが挙げられます。アイルランド出身の著述家ジョセフ・マーフィーは信頼関係についてこのような言葉を残しています。
信頼とは信頼に値する材料があるからするというものではなく、まず先に信頼してしまうことなのです。信頼されると人はそれにこたえようとするものです
相手に何かを求めるのではなく、自分からアクションするという事が大切です。相手に好奇心を向けるとはまさに先に相手を信頼する行為だと言えますよね。
米国の実業家デール・カーネギーは相手に対して好奇心を向ける方法をこのように残しています。
人は誰でも、他人よりも何らかの点で優れていると考えていることを忘れてはならない。相手の心を確実に掴む方法は、相手が相手なりの重要人物であるとそれとなく、あるいは心から認めてやることである。
好奇心を向けるには目の前の相手が何かしらの意味で重要人物だと敬意をもって接する事が大切です。
下記の記事ではほかにも聞き上手になるための方法をお伝えしておりますのでご興味のある方はご覧ください。
3.聞く耳を持つ

あなたは人が最も好きな事を知っていますか?それは自分の話を聞いてもらう事です。逆に最も不快になる事はつまらない話を延々と聞き続ける事です。
人と信頼関係を築こうという思いが強いあまり、自分の話だけをぺらぺらと話す人がいますが、これでは逆効果と言わざるを得ません。人を不快の荒波に落とし込むだけです。
では、どうするべきか?それは相手の話を真摯に聞く姿勢を持つ事です。相手に好奇心が向かっていれば、自然と相手の話に耳を傾けようとするようになるでしょう。
相手の話を真摯に聞く事で相手は次第にあなたに心を開いて来るようになることでしょう。
下記の記事では聞く耳を持つための最高の手法であるコーチングスキルのやり方をまとめさせて頂きました。第2章職場の人間関係を劇的に改善するコーチング的攻めの聴き方6カ条にて詳しくお伝えしておりますのでご興味のある方はぜひご覧ください。
4.横のコミュニケーションを心掛ける

私たちコーチは常に横のコミュニケーションを心掛けています。一方、世間一般に浸透しているコミュニケーションの方法は上下のコミュニケーションです。上下のコミュニケーションは対立のコミュニケーションとも呼ばれています。
横のコミュニケーションとは自分も相手も同じひとりの人間として立場や年齢の差こそあれ対等に大切な人として接するコミュニケーション方法です。どちらも大切な存在という部分がキーポイントです。
逆に、上下のコミュニケーションとは立場や年齢の差など一方が上、一方を下と認識してのコミュニケーション方法です。
命令する事は上下のコミュニケーションの代表例です。また、ほめる事も上下のコミュニケーションに入ります。そして、アドバイスをするなども上下のコミュニケーションとなります。
コーチングでは上下のコミュニケーションは一切使いませんが、普通の会話で上下のコミュニケーションを全て廃止する事は難しいでしょう。しかし、上下のコミュニケーションを減らし、横のコミュニケーションを心掛けるだけで人との信頼関係は大きく育まれて行きます。
では、あなたは横のコミュニケーションとはどのようなコミュニケーションだと思いますか?
横のコミュニケーションの種類
部下が上司にアドバイスをしたり、ほめたりしたとしたら、上司はいい気分にはならないでしょう。それはアドバイスやほめる行為が主に目上の者が目下の者に対して使うコミュニケーションだからです。
横のコミュニケーションは対等のコミュニケーションとも呼ばれています。上も下もなくおたがいひとりの人間として尊重しあうコミュニケーション方法です。
自分を大切にし、相手を大切にするコミュニケーション方法と言えるのです。そんな横のコミュニケーションの種類についてみて行きましょう。
1.ユー(You)クエスチョン
横のコミュニケーションの代表的な例はあなたを主語とした質問です。この質問はユークエスチョンと呼ばれています。日本語では主語はあまり使いませんが、相手に対して気持ちを聞く質問をする事と意識すると分かりやすいかも知れません。
- (あなたは)何をしたいのですか?
- (あなたは)今の話を聞いてどう思いました?
- (あなたは)この状況から何を見据えているのですか?
このように相手の心情を聞く質問をユークエスチョンといいます。相手に寄り添った質問という事ですね。寄り添うという所が横のコミュニケーションのポイントでもあります。
2.アイ(I)メッセージ
アイメッセージとは自分の気持ちを相手に伝えるコミュニケーション方法です。
特に相手に対して要望を伝えたい時におすすめです。これに対してユーメッセージがあります。(※ユークエスチョンじゃありませんよ。)ユーメッセージも相手に対して要望を伝えるのですが、対立の要因になってしまうのです。ちなみにユーメッセージは上下のコミュニケーションとなります。
例えば、相手に対してもっと静かにしてもらいたいという要望を出すときを考えて見ましょう。
ユアメッセージの場合
うるさいからもっと静かにして。(相手に対して向かうメッセージ)
アイメッセージの場合
うるさいと仕事に集中できなくてとてもつらいから静かにしてもらえないかな?(自分の気持ちを伝えるメッセージ)
ユーメッセージとアイメッセージではメッセージを受け取る時のインパクトが大きく異なります。相手に対して向かうメッセージでは対立が起こってしまいかねませんが、自分の気持ちを伝えるメッセージでは対立は起こりにくいのです。
アイメッセージは相手をひとりの人として尊重するメッセージだからこそ対立になりにくいのだと言えるでしょう。
アイメッセージについて詳しくは下記のリンクをご参照下さい。第3章自分の気持ちを伝える話し方がイライラした対立を生まない4つの理由にてアイメッセージに関して詳しくお伝えしております。
3.非暴力コミュニケーション
非暴力コミュニケーションは自らの主張を対立を起こすことなく伝えるために作られたコミュニケーション方法です。アイメッセージに似ていますが、アイメッセージよりもはるかに主張が通りやすい事が特徴です。
非暴力コミュニケーションの一連の流れです。
- 観察を評価・判断交えず伝える
- 感情を伝える
- 求めているものを伝える
- 要求を伝える
先ほどの例に挙げたうるさいから静かにして欲しいという要望を非暴力コミュニケーションで伝えたならばこのようになります。
あなたが2階で遊んでいた1時30分から2時までの30分間、1階にまで聞こえるほど騒音がうるさかった。(1)私は仕事に集中できないとつらいんだ。(2)明日しっかりと休むためにも、今日中に仕事を終わらせたいんだ。(3)だから、静かにしてもらえないかな?(4)
このように非暴力コミュニケーションの一連の流れを踏んで伝えていく事で自分の要求を通しやすくなります。めんどくさい方法だなと思う方もいらっしゃるとは思いますが、このメッセージを使いこなす事が出来れば人との対立は劇的に減って行きます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
人との対立が劇的に減れば、信頼関係を容易に築く事が出来るようになって行く事でしょう。
4.ありがとう

人にアドバイスをしたり、ほめるのは上下のコミュニケーションでした。上から下に流れる性質を持つ言葉だからです。しかし、ありがとうという言葉は全ての人に平等に受け渡す事が出来る言葉です。
コーチングの原点ともいえるアドラー心理学では上下の関係を否定し、横の関係を推奨しています。上下のコミュニケーションには「能力のある人が能力のない人に下す評価」という側面が含まれているからです。
対人関係を縦でとらえ、相手を自分より低く見てしまうことで人は他者に介入をしてしまうのです。これでは自らを低く見積もられている人の意欲を沿いでしまいます。
このような上下のコミュニケーションでは人は奮い立たないというのがアドラー心理学で伝える所です。
では、アドバイスをしたり、ほめるといったコミュニケーションを使わず、人が奮い立つコミュニケーションとはなんでしょうか?それをアドラー心理学では「勇気づけ」と呼んでいます。その言葉こそがありがとうという言葉なのです。
ここで大切な事は他者を評価しないという事です。ほめるという行為は他者を自分の物差しで評価していますよね。しかし、ありがとうという感謝の言葉は純粋にその人に向かう言葉です。そこに評価・判断の物差しはありません。
このように、その人自身に向かい、自分が自分でいいんだという勇気づけをもらえるコミュニケーションこそが横のコミュニケーションなのです。自分に勇気をくれる人と信頼関係を築きたいと思うのは人として当然ですよね。
アドラー心理学について詳しくは下記のリンクをご覧ください。
5.共感力を身に着ける

共感力を身に着ける事も人と信頼関係を築く上でとても重要です。自分の話を共感して聴いてくれる人がいたら当然信頼しますよね。それほど、人は自らを分かってもらいたいという気持ちを心のどこかで持っています。
でも、共感力なんてそれこそ持って生まれたもので身に着けようがないんじゃないか?とあなたは感じているかもしれませんね。大丈夫。ご安心下さい。現代科学で証明されているのですが、共感力も実は後天的に身につけられるものなのです。
では、どうやって共感力を身に着けるか
それは脳内で分泌される幸せホルモンオキシトシンが大きく影響しています。この幸せホルモンオキシトシンを分泌させる事が共感力を身に着ける上で必要不可欠です。
オキシトシンを定期的に分泌させていく事で、次第に日常的にこのホルモンの恩恵を受ける事が出来るようになります。
この幸せホルモンオキシトシンは幸福感を味わうだけでなく、共感力をあげたり、免疫力をあげたりと神秘の秘薬のように効果・効能が素晴らしいのです。
幸せホルモンオキシトシンの分泌方法について詳しくは下記のリンクをご覧ください。
また動画でも詳しく説明しております。
6.ボディーランゲージを意識する

ボディーランゲージに詳しくなくても、目の前の相手が顔を下に向け、両腕両足を汲んでいたらかなり緊張状態にある事が分かりますよね。もし、あなたが信頼関係を築こうとしている人の前でこのような姿勢を取っていたら信頼関係を築くなんて夢物語に終わってしまうでしょう。
心理学者のアルバート・メラビアン博士は、話し手が聞き手に与える影響がどのような要素で形成されるか測定しました。 その結果、話し手の印象を決めるのは、「言葉以外の非言語的な要素で93%の印象が決まってしまう」ということがわかりました。
視覚情報 (Visual) – 見た目・身だしなみ・しぐさ・表情・視線 …55%
聴覚情報 (Vocal) – 声の質(高低)・速さ・大きさ・テンポ …38%
言語情報 (Verbal) – 話す言葉そのものの意味 …7%
実は、言語的な部分は1割にも満たない、7%しか相手に伝わらないのです。
目は口ほどにものを言うとはまさにその通りで、私たちが発する情報は言語情報以外の方がはるかに多いと言う事ですね。
よって、言葉だけでなくボディーランゲージに意識を向け、自分の印象をよりよく見せる事が出来れば、相手のあなたに対する印象は大きく向上して行く事でしょう。信頼関係を築く上で相手からよい印象を持たれることは大切です。
ボディーランゲージに関して詳しくは下記のリンクをご覧ください。
7.感謝の気持ちを表現する

相手に対して感謝の気持ちを表現する事は信頼関係を築く上でなくてはなりません。人にはミラーニューロンと呼ばれる神経細胞があります。この神経細胞はまるで相手と同じ行動をとっているかのように感情が反応することからミラー(鏡)ニューロンと名づけられました。
当然、感謝の気持ちを表現する時って人は自然と笑顔になりますよね。あなたの感謝の笑顔を見た時に、相手もあなたへ対して感謝の気持ちと笑顔が沸き上がって来るという事ですね。
当然、妬みや憎悪の気持ちが表現に出ていれば、相手からも同様の感情が帰って来るという事ですね。心理学ではこの心理を鏡映と読んでいます。
面白いことにここでも鏡という文字が使われるんですね。
人と信頼関係を築く上で感謝の気持ちを表現する事はとても大切な事なのです。
まとめ
今回の記事では人と信頼関係を築く方法について書かせて頂きました。まだまだ、書き足りないことがたくさんあるのですが、ひとつの記事としてはボリュームがかなり長くなってしまいましたので、書き足りない部分は今後の記事で書いて行こうと思います。
人と信頼関係を築くにはまずはなによりも自分自身を向上させていく事が大切です。そして、自分自身を向上させる方法は適切なやり方で行っていけば遠回りせずに最短の道を歩むことが出来ます。今回の記事では自分自身を向上させる最短の道をお伝えしています。どれも私が日ごろから意識をしている事ばかりです。
そして、これらの事を意識するようになってから心がとても楽になって来ました。
過去の私は、自己受容できていないため、自らを責めつづけ心が疲弊していた時期が長く続いていました。そのため、身体に慢性的なコリとなってストレスが表れてくるほどでした。
過度にいい人でいつづけようとしたために、自分をないがしろにし、人の都合を最優先していた時期もありました。ようは、自分自身を大切に扱う事が出来ていなかったという事ですね。
今では自分自身を大切に扱う事を最優先しています。人の事よりも何よりも自分を大切に扱ってあげることが出来るようになりました。そして、自分自身に対して受容出来るようになりました。
自分を受け入れる事が出来た事で、他者を心から受け入れる心のスペースが出来て来たのだと思います。いい人でなければいけないと思い込んでいた以前の私であれば他者の要望を受け入れ続けている事に大きなストレスを感じていましたが、今ではそれはありません。
自分自身を大切にする事が出来ているため、心の防衛機能が強化され、心にゆとりが出来ているのが大きいのでしょう。
今回の記事全般において言える事なのですが、自分自身を本当の意味で大切に扱ってあげる事が人と信頼関係を築く上でなによりも大切な事だと言えます。
この記事を最後までご覧いただきありがとうございました。
下のリンク記事は自己実現ラボにおいて書かれたコミュニケーション能力を向上させるために必要な記事をまとめさせて頂きました。コミュニケーション能力を向上させたい方は下のリンク記事をご覧いただく事でご自身にあったコミュニケーションを高める方法を手に入れる事が出来るようになるでしょう。あわせてご覧ください。











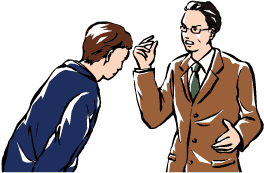

コメント